劉慕沙/譯,《女身》,遠流出版社,1991年。
女であること (新潮文庫) 文庫 – 1961/4/18

川端 康成 (著)
恋愛に心奥の業火を燃やす二人の若い女を中心に、女であることのさまざまな行動や心理葛藤を描いて女の妖しさを見事に照らし出す。
内容(「BOOK」データベースより)
女人の理想像に近い弁護士夫人市子や、市子を同性愛のように慕いながら、各自の恋愛に心奥の業火を燃やす若い二女性を中心に、女であることのさまざまな行動や心理的葛藤を描いて女の妖しさ、女の哀しさをみごとにとらえた名作。ここには、女が女を知る恐怖、女の気づかぬ女の孤独と自負が、女の命のなまなましさと無常の美とをたたえながら冷酷に照らし出されている。
這本女身和他其他的作品不同。 一般的川端康成的女主角都是清麗又嫻雅的人物,如雪國的駒子,古都的千重子。女身的第一女主角榮子則有別於這些女子,她是個活潑的女郎,漂亮又嬌縱,整天咭咭呱呱,鲜蹦活跳的。 事情是這樣的: 榮子討厭鄉下家庭的生活,到東京投奔媽媽的同學市子阿姨和她的律師丈夫佐山。 剛巧,市子兩夫婦收容了一位殺人犯的女兒妙子 - 一位感情纖細又有點神經質的少女。 原本佐山、市子和妙子三人的生活是安安靜靜的;榮子闖進來後把這安靜的生活徹底顛覆。 榮子把妙子迫得搬出市子家,還和市子發展了一段曖昧的同性戀關係,以及和佐山及市子的前男朋友有過一段不倫之戀。
http://bookdejour.blogspot.com/2013/04/blog-post.html
川端 康成 (著) 劉慕沙/譯《女身》女であること

----
川端康成の世界
詳細情報
| タイトル | 川端康成の世界 |
|---|---|
| 著者 | 川嶋至 著 |
| 著者標目 | 川嶋, 至, 1935-2001 |
| 出版地(国名コード) | JP |
| 出版地 | 東京 |
| 出版社 | 講談社 |
| 出版年月日等 | 1969 |
| 大きさ、容量等 | 298p ; 20cm |
| 価格 | 580円 (税込) |
| JP番号 | 75017685 |
| 出版年(W3CDTF) | 1969 |
| 件名(キーワード) | 川端, 康成, 1899-1972 |
| NDLC | KG510-カワバタ,ヤスナリ(川端康成) |
| NDC | 910.28 |
| 対象利用者 | 一般 |
| 資料の種別 | 図書 |
| 言語(ISO639-2形式) | jpn : 日本語 |
| 1956年(昭和31年) | 56 - 57歳。英訳『雪国』がアメリカで出版。3月から『女であること』を連載発表。 |
-----
「近代文学論集」(編集・発行:日本近代文学会九州支部、1999年10月、25号、64-73頁)
(This Japanese article "Sorihashi ni Okeru Hashi: Shocho to Kaishaku" was originally published in Kindai Bungaku Ronshu (published by Nihon Kindai Bungakukai Kyushu Shibu),Vol.25,1999, pp.64-73.)
ダニエル・ストラック 北九州大学文学部比較文化学科
「反橋」における〈橋〉
――象徴と解釈――
ダニエル・ストラック
はじめに
川端康成の「反橋」は彼の代表的な連作の一部を構成するが、本作品における〈橋〉の象徴的機能を探求することは今までの研究において十分になされていないので、〈橋〉に焦点をあてた解釈を行いたい。〈橋〉は多様な象徴性を持ちうるシンボルであるからこそ、その登場によって様々なニュアンスが物語に付加されるのである。ドイツの哲学者・評論家ゲオルグ・ジンメルは、〈橋〉は芸術作品において実用的意義を象徴すると同時に、直感的に認識される形式も持つからこそ、他の自然の風物よりも緻密な表現力を持ち、橋への理解が偶然に左右される可能性も遥かに少ないため、特徴的な象徴であると指摘している。(1) 「偶然性」によって左右されることの少ない〈橋〉は古代から文学作品における象徴として多くの作品に貢献してきたが、川端の「反橋」はまさにその一例である。〈橋〉の多義性を伴った象徴性は作品に心理的余韻を付加することを確認した上で、作品における〈橋〉は中心的イメージであるのみならず、作品を支配するメタファーでもあることも明確ににしたい。併せて「反橋」の橋が持っている象徴性と類似した象徴性を持つ〈橋〉が日本文学や世界文学に登場している例を考察したい。
「反橋」の構成とプロット展開
「反橋」という短編は「住吉」連作の一部とみなされている。その他の作品は少なくとも「しぐれ」と「住吉」を含んでいるが、「隅田川」も連作に属すると考える研究者もいる。「反橋」と同時代に書かれた「しぐれ」と「住吉」との間には、注目すべき共通点があり、各作品の冒頭と末尾に共通して見られる呼びかけは以下の通りである。「あなたはどこにおいでなのでせうか。」(2)
連作の各作品間には他にも多数の共通点があるかもしれないが、中心的プロットに議論を限定したい。連作の最も重要な共通点が死者の思い出を語ることであるのは周知の事実である。しかし「反橋」
-----pg.64/pg.65
においては、母と「私」の旧友の須山に関する思い出が描かれていて、「住吉」には再び母に関する思い出、さらに「しぐれ」にはもう一度須山の思い出の描写が登場する。各作品には、〈死〉を表現する歌、絵画、物語などの芸術が登場し、〈死〉というテーマが中心となっているのは確実である。登場人物とテーマが共通であるのみならず、住吉という場所は舞台として登場し、連作中の風景描写に大きく貢献しているのである。とりわけ「反橋」において、行平という少年が母と思っていた女性に住吉大社に行かされ、神社の有名な反橋の上で、実母が既に亡くなっており、今の母は彼女の妹、つまり継母であることを教えられる。その時点から「私」の人生は「狂って」しまい、橋の上で初めて感じ取った「あはれ」の感情は、死に直面している現在に至るまで継続している。
しかし、作者はなぜ三つの作品すべてにおいて、冒頭と末尾に、「あなた」の呼びかけを繰り返し使用しているのだろうか。各作品において繰り返されている〈枠〉としてのその言葉は使用されているからこそ、重要であると考えられるのだろうが、この箇所に関しては、従来から様々な解釈がなされている。山本健吉は以下の通り述べている。
「『あなた』とは、生母とも義母とも、あるいは『 ならぬ』仏とも思われる。」(3)「反橋」が書かれた一九四八年の一年前に横光利一が死去したことに注目した保昌正夫氏は、「あなた」が横光である可能性(4)以外にも、「亡き肉親」、「僚友」、「自身の文学」、あるいは「心根のありか」である可能性にも注目し、解釈の幅を大きく認める形でこの個所を理解している。石浜恒夫の指摘によって、作者の「反橋」執筆の動機が明らかになるだろう。
「それによると、昭和二十一、二年ごろ川端は、当時石浜の家の離れを借りていた藤沢恒夫をたずねた。家は住吉にある。そのとき藤沢は以前菊池寛にもらった色紙二枚を見せた。一枚は梁塵秘抄の「仏は常にいませども……」で、他の一枚は「只看花之開落、不信人之是非」であるが、川端は「菊池さんはいい字ですね」「菊池先生はこんな文句が好きなんですね」とつぶやいたという。また川端は石浜の案内で近くの住吉神社に行き、石橋を見、大鳥居の前の露店に足をとめて、桃色の半エリを手にとってじっと見ているという。」(5)現実の住吉大社の反橋は石橋ではなく、石柱に板を敷いたものであるという点以外には、この指摘に疑問の余地はない。しかし作者は読者の理解を容易にするために、現実に完全に基づいた物語を書く必要はなく、逆に作者の実体験を取捨選択せずに書くことは傑作を生み出すことにはつながらないと考えられる。このため、「あなた」の身分に関して様々な解釈が存在することは当然かもしれない。その上、川端自身が「あなた」という曖昧な表現を意図的に使用したからこそ、複数の解釈が同時に成立すると考えることができる。逆に一つの解釈に限定することによって、呼びかけの神秘的響きが失われてしまう可能性もあるに違いない。この点に関しては石川巧氏は「「あなた」とは誰なのかという議論は、その問題設定自体が不毛である」(6)と述べているが、この指摘に筆者は同意する。それが死者、或いは死そのものへの呼びかけである可能性は高いが、結局「あなた」の身分に関して結論を述べるべきではないだろう。
-----pg.65/pg.66
住吉大社と反橋に関して
大阪市の住吉大社にある「反橋」は、中国大陸のモデルが日本に移入され、〈呉橋〉(くれはし)と呼ばれていたものが日本風にアレンジされた橋である。路子工(みちのこのたくみ)という百済からの帰化人は中国風の石橋を約1400年前に日本に紹介したと推定される。しかし、現在の日本に見られる反橋は呉橋と違って、石のみによって作られた建築物ではなく、何本かの石脚の上に木造の床面を敷いたものである。「反橋」の様子は中国の反橋に類似しているかもしれないが、それとは本質的に異なっていることは注目に値する。この相違に関して上田氏は以下の通り述べている。
「地下水位の高い、したがって河川水位の高い南中国のクリーク地帯にかかる橋であるから、舟の航行をかんがえれば自然にそうなるのだろう。それが南中国の橋一般であるば、路子工が橋脚の何本もあるような日本の反橋に似た橋を大陸からもってきたとはとうていおもわれないからである。」(7)
実用性が要求する以上にアーチの傾斜が急な反橋は非実用的であるが、実用性と密着していない橋は日本のみに存在するのではない。アルバニアの代表的作家イスマイル・カダレの小説『三つのアーチの橋』の中に、庭の風景をより美しく見せるための単なる装飾にしか過ぎない橋が登場する。この様な橋は、川などを渡る目的のためではなく、実用性を重視する橋梁設計士にとっての悪夢を体現する「死んだ橋」として登場する。普段、橋の目的は川などの物理的障害を越えることであるのに対して、「死んだ橋」は実用的な用途がないため、本来の橋としての存在価値を持つ必要はない。住吉大社の神池は人造と考えられるので、そのような池を渡るための反橋も「死んだ橋」であると考えられる。
以下に「反橋」に登場する多義性を伴った橋の象徴性を考察したい。比較的自明な象徴性の考察から微妙なニュアンスの考察へと進みたい。各セクションにおいて三項目に分けて説明するが、「反橋」の解釈と同時に日本文学、世界文学における〈橋〉も併せて考察の対象とすることにより、〈橋〉の多義的象徴性を探求したい。
反橋は逆転の橋
多くの研究者は川端自身の生涯と、「反橋」の主人公の間に共通点が多いことに注目している。とりわけ川端は「私」と同様に継母によって育てられたことを考慮すれば、「反橋」のみならず連作中の他の作品においても登場する〈継母と子の関係〉というテーマに、川端自身の心理的状況が多大に反映していると解釈できる。しかも、「反橋」にはこのテーマが緻密に描かれているがゆえに、他の川端の名作に光を当てるロゼッタ石のような存在であることを主張したい。川端は幼少時に実母を亡くしたため、母の妹に育てられたことは羽鳥氏の研究によって明白であるが、川端自身はこの事実を家族から教えられていなかった。林氏は川端の実体験が作品に対して及ぼした影響に関して以下の通り述べている。
「次に、おそらく中学入学時に康成は戸籍謄本を見て衝撃を受け、母に疑いをもったという事情を推察し、初期作品「白い満月」等から康成にこの疑惑を主題とした作の多くあることを例証する。」(8)
-----pg.66/pg.67
「反橋」において作者の心理的状況がある程度描かれている点には疑問の余地がない。しかし、川端が実際に「母の秘密」を教えられていなかったとすれば、川端の母が彼に秘密を橋の上で明かした過去がないと判断する以外にはなく、反橋上での母と子の会話場面は作品を心理的に強調するための方策であることが分かる。反橋での告白がなされる場面が短編の中核を占める以上、〈反橋〉の設定なくしては、物語は成立しないといっても過言ではないだろう。母の発言に対する「私」の反応は大きく誇張された言葉によって描かれていて、自分が「不幸な人生」を送っていた事実がその際に初めて判明したということを表現している。「私」によると、反橋を昇る前は母の実子だった彼が、降りる際にはもはやそうではなくなっている。母は「実母ではない」と伝えた際に泣いていたが、その後も今まで通りに彼の世話することを止める気配はなく、具体的な二人の関係は変わらないが、母は重要な何かが変化したことを伝えようとしている。継母の愛が純粋であったのならば、橋の上の残酷とも映る行為は必要だったのだろうか。しかし、それが残酷に見えようとも、真実を誰からも伝えられずに、実母のことを偶然に学校の書類で知って衝撃を受けた川端自身は、「反橋」の中の描写と同様の〈哀れみ深い〉経過によって真実を知ることを希望していたのではないかと思われる。作中に反橋が使用され、真実に直面する母子に共通する苦痛に対する思耐力が強調されるばかりであるが、作者自身の実体験においては作品に見られるような率直さはなかっただろうと推察できる。この推測が妥当であれば、川端は〈反橋〉の象徴性によって、単純な感情と片付けてしまうことができないような後悔を喚起する事件を自分が納得できる心理的形態に整理したい要求を表現しているといえるだろう。
「反橋」の重要な場面での背景をなす〈反橋〉の代わりに他のアーチ型の橋を描くことは不可能ではないが、「反」(そる)という意味が包含されているからこそ、反橋は完璧なシンボルであるといえるだろう。橋の上で起きた事件によって、主人公の生涯が取り返しのつかない変化をこうむる点が、橋の名前の象徴性と合致していることに注目する林氏は、「その頃から先、悪逆の未来への進行が、高度の絶対値において同時に過去の生の根源への進行でもある、主人公行平の生の軌跡の構図」(9)が反橋の象徴性によって提示されていると述べている。住吉大社にある「反橋」は「太鼓橋」とも呼ばれているが、この名前が持つイメージは短編の内容と一致していないため、「太鼓橋」という名称は当然ながら一度も作品に登場しない。逆に、「太鼓橋」という名称を使用したとすれば、作者が意識的に込めた象徴性は稀薄になっていたに違いない。
日本文学の中に登場する橋は〈宿命に満ちた場所〉である事実に関して、保田與重郎氏や他の研究者は注目しているが日本古典文学において〈橋〉は運命が逆転する場として多く使用されてきたにもかかわらず、〈逆転の場〉を象徴する橋の存在が殆ど明らかにされていない。この〈橋〉の象徴性の登場は明治以降の作品には少ないが、とりわけ浄瑠璃家の近松門左衛門は多義性を伴う〈橋〉の特徴を有効に作品中で活用した。『槍の権三重帷子』において、橋は逃亡しようとする恋人達にとって唯一の救いの道であると映るが、結局二人共、橋の上で女性の夫に殺される。 また『国性爺合戦』においては、敵軍が攻撃に際して橋を利用するが、橋が本物の橋でなく相手を惑わすための雲の橋であったため、万軍の敵はすべて高い
-----pg.67/pg.68
崖から落ちて死んでしまう。勝つはずの強敵が負け、あと一歩で救われるはずの恋人を穴に落とすなど、浄瑠璃においては逆転を起こす橋の機能が綿密に繰り返し描かれているのである。
世界文学において、運命の逆転の場を表現する橋は数多く見られるが、本稿においては詳述する余地がないため、一例のみを取り上げよう。アメリカ人作家アーネスト・ヘミングウェイの第一次世界大戦を描いた『武器よさらば』における橋は、拡張したドイツ軍占領地に残された兵隊に脱出の余地を与えるが、木橋の周辺にいる主人公が洪水状態の川に飛び込み、その後、兵隊から脱走することを考えると、橋は物語の主筋を形成する運命の逆転を起こす存在として登場していることが分かる。
反橋は透視力を与えられる場所
反橋のアーチの上で「得意」になっている「私」に、母は彼の出生に関する真実を教えた。橋は透視力が機能する場所として、文学によく登場するが、作家達のこの傾向を考慮すると、やはり人生の神秘を看破できる所として川端も橋を認識していたことが分かる。広辞苑を引くと という言葉は見つかるが、その定義は以下の通りである。
「はし-うら【橋占】橋のほとりに立って往来の人の言葉を聞き、それによって吉凶をうらなうこと。」(10)
「反橋」は、橋占といえるものではないだろうが、そのようなニュアンスに満ちた作品であるに違いない。〈橋〉は人生の裏面を見極める場所として、文学、民話、伝説などに頻繁に登場する。「反橋」においても橋は作者が人生を抽象的観点に立って見極める所として登場し、実際に彼は橋の上において自分の出生に関する真実を知ったため、この個所においても両方の機能が働いていることが分かる。
この橋占が登場する作品における、もう一つの橋の象徴的役割は異なった時間帯を結ぶ橋の機能である。橋が人生を見極める場所で、同時に川を渡る場所であるのならば、川は人生の象徴として登場し、上流が〈生まれ〉を意味し、下流には海、つまり〈死〉が待っているといえる。橋から全人生が俯瞰できるというこの不思議なシンボリズムもよく描かれている。住吉連作の全作品が人生を回顧するテーマを持つ。川端は自分の過去、遠い昔に亡くなった詩人の詩、つい最近亡くなった須山のこと、母のこと、そして未来に必ず訪れる自分の死に関して思いを巡らす。そこで住吉の反橋は過去、現在、未来に相互の関連性を持たせ、連作の時代の違いを超越した統一性を作り出すシンボルとして不可欠な存在となっている。
〈橋姫伝説〉(11)は日本中に普及しており、とりわけ文学と伝統に関する知識が豊富だった川端の場合、橋と神々の関係を物語に織り込むのが当然だろう。しかも、源氏物語に橋姫が実際には登場しなくても「宇治十帖」の「橋姫」巻があるが、作者は源氏物語に関する主人公の述懐を「住吉」に取り入れ、森本氏は川端と源氏の注目すべき共通点に関して以下の通り述べている。
「孤児であるが故に生涯を漂泊しなければならぬ源氏の運命に、川端は自分の生のありようを見出したのである。」(12)
〈橋姫伝説〉との関連性が少ないとはいえ、「反橋」において「私」の人生が〈橋の女〉が伝えた真実によって損なわれたことを考慮するのが、無視できない共通点である。作者が意図的にこのニュアン
-----pg.68/pg.69
スを取り入れたか否かに関しては判断を下す余地がないが、「反橋」の背景描写の詳細を見ると、僅かとはいえ、この関連性ゆえに興味深い余韻を形成していることが分かる。
反橋が生と死の境界として(仏教)
物語が始まると間もなく作品に「もののあはれ」が溢れてくる。ヨーロッパの絵画と日本の詩という美術的なバランスを保った組み合わせによって極めて緻密に構成された雰囲気が作品を支配することとなる。作品はこの芸術的枠組に支えられ、作者が無常や死に関するより深い理解に到達する予感を読者に喚起する。藤原定家、西行法師、三条西実隆、住吉法楽百首等を巡ってから、主人公は住吉の宿に残した自ら書いた色紙について語る。その色紙の内容は以下の通りである。言及されている舟は仏教用語であり、死後における彼岸への移動が抽象的に描かれていると思われる。不安定な川が多く存在するインドから伝来した宗教においては橋があまり登場しないため、仏教においては橋ではなく、舟によって人間が救われるが、橋は直観に訴える象徴性を持っているため、この舟が持つ人間を救済する能力の描写は仏教の影響を強く受けている日本の文学にも見られる。『住吉の神はあはれと思ふらむ空(むな)しき舟をさして来れば』(13)
「私」は自分が住吉に「行ってはならない人間」であることを告白し、反橋の事件が語られることによって、その意味は読者に明確に伝わる。五歳の時、母に連れられて住吉大社の反橋を登ろうとした際、彼はその急な坂を恐れた。登り切ったところで登るのが思った以上に容易だったことに気づき、その直後に継母が彼の実母について事実を伝える。主人公が伝える反橋事件、亡くなった須山の色紙、死んだ詩人の「もののあはれ」に満ちた感想の、各々の要点を比較すると、全てが、未知の世界や死に対する恐怖というテーマを含んでいる。母が橋上で伝えた「悲しい話」は、須山の色紙の〈悲しい話〉と、亡くなった詩人の〈悲しい話〉と重なることによって、作品全体の基調である無常への方向性に弾みを付ける。「反橋」の設定は複雑で図式で完全に説明することは困難だが、以下の図によって、この積み重なった〈悲しい話の伝達〉という面に限定して詳しく図示したい。
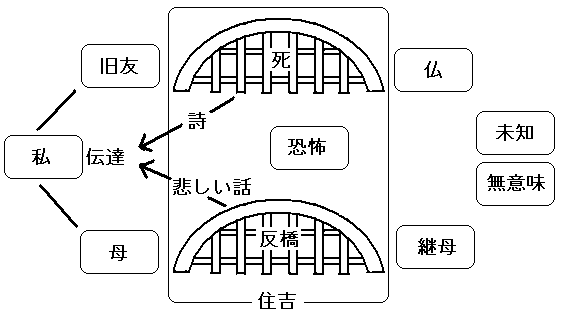
-----pg.69/pg.70
橋の上で馬車に轢かれて死ぬ。日本文学は舟を利用する仏教的な傾向が強いといえども、橋の直観的象徴性がそれを超越している事実は数々の例によって明白となるだろう。
以上に引用したカダレの『三つのアーチの橋』の他にアメリカ人作家のウィラ・キャザーの『アレクサンダーの橋』が例として上げられるが、それに関しては次章において詳述する。橋は死に至る道という象徴性を世界文学の中において最も多く持っているが、この全世界共通の傾向を考慮すれば、仏教文学の影響を受けている日本においても、橋がこの象徴性を反映していることは不思議ではないと考えられるのである。
反橋は人間と神の境界である (神道)
天地創造の伝説を伝える『古事記』のイザナギとイザナミは天(あま)の浮橋(うきはし)(14)から日本を創造したことをふまえると、現代に至るまで橋の宗教的意義に関しては仏教的な解釈以外のものも可能であると認めざるをえない。住吉大社に限らず、福岡県の太宰府天満宮、和歌山県の丹生都比売(にうつひめ)神社や、他の神社にも見られる(「太鼓橋」・「輪橋」ともいう)反橋は日本の他の神社にも存在する。〈反橋〉は大通りに至る橋とは異なって、その実用性よりも装飾性に重点がおかれている。しかし、神社にある橋の最大の役割は宗教概念に基づいている。筆者は住吉大社の住職と実際に会話を交わしたが、彼は反橋の目的は鳥居と同様に俗世界から神聖な領域に入ることを意識させることであると述べた。橋を渡るのと同様に、神社の聖なる領域に入る際に昔から禊(みそぎ)で手を洗う習慣も見られるが、水を越えることはその禊に代わる行為と思われる。
日本にある反橋はもとから反橋と呼ばれていたのではなく、呉橋と名乗っていたのである。呉橋の歴史に関して、上田氏は「呉橋はその須弥山にむけてかけられた「聖なる橋」だった」ため、「その橋をわたるのは、人間でなく神様なのである」と述べている。(15)能の世界においても「橋懸り」(はしがかり)は楽屋と舞台をつなぐ、役者の登場と退場の際の通路として用いられているが、「この橋は、はるかなる異次元の世界と現世を結ぶ橋である」。(16)住吉大社にある反橋と同様に、「反橋」に登場する橋は、人が川を渡るという日常的役割のみを果たしているわけではないだろう。おそらく、その橋は作品に装飾として登場しているが、「反橋」の持つ神道的ニュアンスにより、神々が定める、避けられない運命の元におかれた人間の無力さを表現している。住吉大社の反橋は「神池」(17)を越えるために設けられているが、その池も神社内の人造池であるので、ある意味でカダレ氏が説明した〈死んだ橋〉に属するのではないかと思われる。作品においても装飾的な〈死んだ橋〉として機能するのが、「反橋」の背景である神社においてであることを考慮に入れれば、橋の神道的意味が作品に端を発していることは偶然とはいえないだろう。
反橋は人間関係を表す
芸術作品において橋には登場人物の間の距離感を縮める効果がある。恋愛小説において橋は恋人たちの関係を意味し、新聞を見ると政治的次元における国同志の信用と協力のシンボルともなっている。しかし、橋は一方通行ではなく、相互交流を可能にする存在である
-----pg.70/pg.71
ため、相手への接近が生じる一方で、逆に相手から離れて行く方向性も生じ得る。「反橋」における橋は母と息子の関係を表すシンボルであると同時に、その関係の破綻の象徴としても有効に機能することは、作者の橋の選択によって成立しているのである。短編を支配するシンボル〈反橋〉はこの両義性を通して、母と息子の関係の心理的破綻を巧みに表現している。この微妙な両義性が維持されなかったとすれば、「反橋」は強い印象を与えなかったに違いない。
宮本輝の『泥の河』においては大阪の川が舞台となっており、子供たちが相手の所に行く際、必ずと言っていいほど橋を渡らなければならない。二人の子供と互いの家族が〈橋を渡る〉ことによって親近感を強めていくが、やがて橋がないため、その関係に破綻が生じる。(18) 古典文学においては恋愛関係を象徴する橋を数多く指摘できるが、保田與重郎は『万葉集』、『枕草子』などに見られる橋を人間関係の象徴と解釈している。(19) 現代文学においては永井荷風の『すみだ川』や樋口一葉の「にごりえ」にも類似した象徴性を持つ橋を見出せる。
人間関係を象徴する橋が登場する代表的な小説は、前述したアメリカ人作家ウィラ・キャザーの『アレクサンダーの橋』である。この作品において、ある有名な橋梁設計者の人間関係全てが〈橋〉を媒介として成り立っている。橋梁を架す際、妻となる女性と会い、三角関係に陥る恋人ともやはり橋を通して知り合う。主人公はそれらの女性二人から一人を選択しないといけないまさにその時に、橋の建設現場における事故で亡くなり、強度のバランスが取れなかった巨大な橋が一瞬にして崩壊すると同時に、人間関係の限度を越えた橋梁設計者は自分が犯した過ちの犠牲となる劇的な結末となっている。ところで、この作品においても以前に本稿で論じた〈生から死へ〉という方向性を象徴する橋が見られる。
川端の「反橋」を『アレクサンダーの橋』と比較した際に注目すべき事実は、「反橋」においては人間関係の破綻が橋の崩壊を用いないで表現されている点にある。〈反橋〉という特徴を持つ橋の存在を通して登場人物の心理的破綻のみが描かれ、物語の全体的風景に合致しない事故の描写などは省略されている。〈橋〉が登場する他作品と比較して、「反橋」は川端の独創的な〈控えめの美学〉が反橋の特徴を利用して生かされていることが分かる。
心理的障害を克服する〈橋〉の象徴性
橋の最も基本的な象徴性は物理障害を超越する機能に関連している。昔から人間と動物は自然に橋を利用している。人間は結局橋を作ることになったが、橋を作ることよりも、橋を渡る意識の方が人間の橋に対する感覚の原点といえるだろう。橋は川、谷、海などを越えるための単なる道具であるが、ジンメル氏はこの橋という道具の哲学的、心理的本質に関してこう述べている。
「この障害を克服することによって、橋はわれわれの意志の領域が空間へと拡張されてゆく姿を象徴している。」(20)
橋の心理的障害を克服する側面も「反橋」に貢献している。 橋に向かう「私」は母に「強くなった」時に反橋を自分で登ることができると言われたので、彼には「未知へと渡る勇気」があるだろうと母は判断する。 子供時分の「私」はこの質問の背後の意味を理解できなかったが、母は息子が反橋を登り切ることができるとしたら、
-----pg.71/pg.72
彼は既に人生の苦難に直面できる年齢に達していると判断した。母は何故そのような恐ろしい真実を子供に明かしたのだろうか。作者はこれに関して、継母は嘘を付く人生に耐えられなくなったためと答えている。この反橋事件の設定を考慮すると、二人共に障害を越えなければならない状態にあった。主人公は彼の人生に隠されていた不幸と取り組まなければならない。母はそれを彼に伝えるのが恐ろしかったので、伝えるためには勇気が必要であった。主人公が勇気を出して登った際、母も彼に〈悲しい話〉を伝えるのに必要な勇気を持つことができた。短編の最終場面において年老いた主人公が再び反橋を眺める際、つい最近亡くなった友人須山の死のことを考えている。死は誰にとっても恐ろしいものであろうが、子供のころに「悲しい話」を聞いた場所である反橋を見て、これから自らの人生においても死に直面する勇気を持たなければならないことを実感する。反橋には「足たどり」があると主人公はいうが、この足たどりは何を象徴しているのだろうか。絵画が内容と枠の組み合わせによって人々を魅了するのと同様に、この物語を支配しているイメージとしての反橋とそれに囲まれるような美学的随想は無関係とは思われない。既に亡くなった他の詩人の詩は(死人の死は)反橋の足たどりに相当するものである。紹介される様々な芸術作品によって、須山が亡くなったことに伴う恐怖のみならず、語り手自身もいつかは迎える死という〈悲しい話〉に伴う恐怖も和らぎ、「私」はそれを認めることになるだろう。羽鳥徹哉もこれと同様な解釈を行っている上に、「育ての母は一種の足場の如きものである」(21)とも言っている。最後に「私」が反橋を眺めつつ回顧する際、自分の死はそう遠くはないだろうと思っている描写を考慮すれば、やはり以上の解釈は妥当と思われる。
まとめ
「反橋」に関する論文を読むと、「反橋」に登場する橋は、〈石橋〉(22)或いは〈木橋〉(23)と呼ばれているが、実際に住吉大社にある実物は木と石が合体したものであることが分かる。〈反橋〉建設に必要な技術は複雑であるのと同様に、〈橋〉の多義的描写が存在しなければ、「反橋」の世界は成り立たないといっても過言ではない。逆に「反橋」においては川端の洗練された美学と彼の言葉のイメージに関する優れた感受性を再確認することができる。シンボルとしての〈橋〉は世界中の文学に当然ながら存在するが、川端は〈橋〉が持ちうる象徴性を十分に理解した上で、世界中に見られる普遍的な象徴性と日本独自のニュアンスとを巧みに作品中に併存させることによって、「反橋」という傑作を生んだのである。
====================
(1) ゲオルグ・ジンメル 『橋と扉』(一九九八年、白水社)三八頁。(2) 「日本の文学 38:川端康成 」「反橋」(一九六四年、中央公論社) 四五四、四六〇頁、「しぐれ」(同書) 四六一、四六六頁、「住吉」(同書) 四六七、四七三頁。
(3) 林武志『川端康成戦後作品研究史・文献目録』(一九八四年、教育出版センター)二九頁。
(4) 同書、三二頁。
(5) 同書、三四頁。
(6) 石川巧「秘すれば花なり、秘せずれば花なるべからず:「反橋」三連作―川端康成論(四)」『叙説』XVI(花書院、一九九八年二月)三七頁。
(7) 上田篤『橋と日本人』(一九八四年、岩波新書)一七八頁。
(8) 林武志『川端康成戦後作品研究史・文献目録』(一九八四年、教育出版センター)四二頁。
(9) 同書、四六頁。
(10) 新村出編『広辞苑、第四版』(一九九七年、岩波書店)二〇五五頁。
(11) 柳田国男『柳田国男集』第五巻、第五巻(一九六八年、筑摩書房)二一四頁。
(12) 森本穫『魔界遊行――川端康成の戦後』(一九八七年、林道舎)三九頁。
(13) 「日本の文学 38:川端康成 」「反橋」(一九六四年、中央公論社) 四五八頁。
(14) 「日本古典文学第一巻:古事記」(一九七八年、角川書店)五三頁。
(15) 上田篤『橋と日本人』(一九八四年、岩波新書)一八一頁。
(16) 河竹登志夫「橋懸りと花道」(一九九八年、『日本の美学』二八号)八一頁。
(17) 『住吉大社』(住吉大社社務所)四八頁。
(18) ダニエル・ストラック「宮本輝の『泥の河』における象徴 ―〈舟〉と〈橋〉の対立」 (一九九八年、北九州大学文学部紀要第五六号)。
(19) 保田與重郎 『日本の橋』(一九九〇年、講談社学術文庫) 四三頁。
(20) ゲオルグ・ジンメル、『橋と扉』(一九九八年、白水社)三七頁。
(21) 羽鳥徹哉『作家川端の基底』「川端康成、母の秘密と身替りの母」(一九七九年、教育出版センター)一〇二頁。
(22) 森本穫、平山三郎編『注釈:遺稿「雪国抄」・「住吉」連作』(一九八四年、林道舎)二七頁。
(23) 林武志『川端康成戦後作品研究史・文献目録』(一九八四年、教育出版センター)三四頁。
-----pg.72/pg.73
沒有留言:
張貼留言